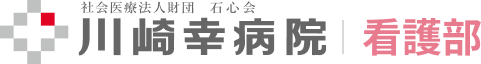今年度は梅雨明けが例年より少々遅めでした。
梅雨が明けたと思ったら、あっと言う間に
危険な暑さまで気温が急上昇です。
熱中症注意報が天気予報番組でも通常の放送内容になりました。
毎日危険な暑さと湿度の中で生活していることになります。
小まめに水分補給とか、よく聞きますが、
小まめにってどのくらいの間隔?と疑問に思いませんか。
大枠ですと、1時間毎くらいに1、
もっと細かくだと10~15分おきにと、目安にされています。
10~15分おきですと、一口二口の水分をちょこちょこと飲む感覚です。
大人でしたら、1日の水分1.5リットル以上と言われてます。
ちなみに「喉が渇いた」と感じた時には、すでに体の水分は
2%程度失われているそうです。
のどの渇きを感じるまえに水分補給ができるのが理想です。
Category Archives: 未分類
熱中症注意報はすでに警報レベル
熱中症の7つのサイン
1.体温の上昇
2.汗をかかない、または、かきすぎ
3,意識の混乱、または歩行困難
4,頭痛
5,めまい、吐き気、嘔吐
6,皮膚が赤くなる
7,心拍数の上昇、または呼吸困難
これは、愚息の通うジム入り口に張ってありました。
「7つのうちのいすれか一つでも症状があれば、
熱中症の危険性が高まります。
暑い夏は、ためらわずに休憩を取りましょう」。。と。
よく読んだら、アスリートの安全と能力に、暑さが与える影響を
研究している人の注意書きでした。
流石にこの時期、外でのワークアウトは厳しいです。
暑い中で運動する場合は、水分補給は落ちろんですが、
適度な休息を挟むこと、さらに準備運動の重要性もあります。
これから高校野球のシーズンです。
熱中症対策を怠ることなく、活躍されることを望みます。
プールサイドの子供たち
久しぶりにプールに行ってみました。
なんとなく泳ぎたいな・・と考えたのですが、時期がまずかったです。
本当に久しぶりだったので、
柔軟体操も行ってからプールサイドへ。
しかし・・・
7月後半はお子さんたちが夏休みなるものに突入していました。
KIDSスクール開催だったらしく、
プールサイドには細かい者たちがわらわらと。
そして、ビート版でチャプチャプしていると、後ろから、細かい者たちが
わらわらと泳ぎ始め・・・
おばさんどいて~と宣うのでした。
おねいさんとお呼びって言ったら、あはは・・・って。
あはは・・・って、なに。
顔と名前の一致
顔と名前が一致しないって、英語でなんて言うのかなと調べてみました。
意外と載ってました。
For the first part, you can say
“I know that person, but I don’t remember their name!”
For the second, you can probably say
the person’s name, and then try to describe them.
顔と名前が一致しない・・と最近記憶力の衰えを感じまして。
病棟時代は患者ーkeypersonー病名ー術式など、覚えられたのに。。。
今から10年程度前までは、スタッフ300名くらいの顔と名前はギリギリ記憶できました。
最近は500名越えてきましたので、時々えーっと・・・となります。
でも入職時の写真と名前を何度も見て、記憶するように勤めています。
記憶の容量が少なくなりつつある中、脳みそにゲキを飛ばしています。
名前で呼ばれた方が絶対うれしいと思うのです。
しかし大変なこともあります。
一重が二重になったり、眼鏡がコンタクトになったり、髪形が変わったり、
意外と印象が変わるものなのです。
看護とAI 隠れているもの
名もなき看護
という題名のコラムを読んでいました。
自動化、マニュアル化で業務がシステム化していく中でも、
例えば連携ミスなどで、妙に時間をとられたり、順番が違ったりする
そんな経験は誰にでもあると思います。
病院であれば、次からは他のところにしようとか・・考えてしまうかも知れません。
例えば待ち時間が多少長くても、システム化されてなくて手作業でも
「今日は込んでいますね。
あと2名くらいで呼ばれると思います。もうしばらくお待ちいただけますか」とか、
「最近の体調はいかがですか」
などの声かけがあると、安心感が与えられると言われています。
業務効率は必要です。システム化も大切です。
では看護は・・・システム化できる部分とできない部分があると思います。
マニュアルには「声かけ」とは載っていないかも知れませんが、患者さんに安心・安全を
与えるという点では看護です。
AIが発達しても、気配を察知して声をかけるのは難しいのではないかと・・・。
看護とは、もう一度考えてみても良いのではないですか。
明日から、と考えることはまずいですか?
最も危険で有害な習慣は、恐らく“一日延ばしの癖”です。
一度何かを引き延ばしてしまったら、再び引き延ばすのは簡単で
ついにはその習慣が定着してしまい、逆にその習慣から抜け出すのが
難しくなってしまいます。
この習慣の治療法ははっきりしています。行動することです。
・・・・うわぁぁぁぁぁ
私が提唱している「明日やる経」を真っ向から否定されました。
「明日やる経」とは、
「今やらなくても大丈夫な事は、明日に回して。
優先順位をきちんと考えて、今やらなくてはいけない事を片付ける」
限られた時間で効率的に業務を遂行するためには、後回しの必要な事もあるということ。
都合よく考えて、、、というより「まっ、いっか。明日で」的発想ではあります。
そんな時に、自分自身の悪い考えを見透かされたような文章が目に飛び込んできました。
すいません。
明日から、治します。
コミュニケーション力とは
言語というものは時代とともに変化します。
同じ言語を使用しているはずなのに、会話がかみ合わないと感じることがありませんか。
日本語のすれ違いには
1.語句を理解しない
例)「時系列で考えましょう」
「時系列?」
双方の語彙力に大きな隔たりがある場合
2.語句の意味の理解が不正確
例)A「たびたび電話してくるんだよね」
B「毎日は迷惑だね」
A「毎日じゃないんだけど」
B「たびたびって言うから毎日かと思った」
語句の意味を自己流に解釈するとこうなる。
言ってないことが言ったことになるのが、このパターン。
3.表現、意図を理解しない
例)A「そのうち飯でも」
B「来週ですか、今週ですか」
相手がどんな意図で言ったかを理解するのは難しい。
この反応が返ってくる人とは距離を置いてはいかがか。
事例を書いていた方は「国語辞典編さん者」言葉のプロの方です。
「文脈を理解しない」という例もありました。
コミュニケーション力という力を重要視する企業も増えていると聞きます。
きちんと対面で、お互いに理解し合える会話をしたいと思います。
父の日
五月晴れ
熱中症注意報
昼夜のみならず、毎日が寒暖の差が激しく体調管理の難しい時期です。
特に日中の気温と湿度には、注意が必要です。
室内でも少し動くと汗ばんだりしますので、屋外では更に注意が必要です。
本来は5月といえば爽やかな季節、新緑が濃くなる良い時期のはずですが、
最近は日本のみならず、世界的に温暖化が進み、気温が上昇していますね。
日本はもはや亜熱帯地方に近いのではないでしょうか。
我が家も外出時にはお互いに水分補給を心がけ、体調が悪いと思ったら
無理をしないでと声を掛け合っていたのですが。
愚息から届いたメールが
「ドライガンガンで洗濯物乾燥戦法実施中。さむい」
。。。そういうのが、温暖化を進めてしまうのでしょうーが!
皆さん、エアコンの使用は適切にお願いいたします。