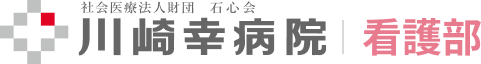酒は適量を飲めば健康に良く、どんな薬よりも効果のある薬である
(所説あります的な・・・) という意味で用いられることが多いと思います。
古代ギリシャの医師であったヒポクラテスは、ワインを最も有益な薬であると称えていたそうです。
では、医学的観点ではどうなのか?
酒を適量飲むことで
アルコールがLDL(悪玉)コレステロールの増加を抑え、HDL(善玉)コレステロールが増加すること、
血液が血管の中で詰まりにくくなり、心筋梗塞や狭心症など虚血性心疾患の予防効果があるそうです。
ですがー、飲みすぎると
中性脂肪が増加し、HDLコレステロールの低下、LDLコレステロールの増加、
血圧上昇や高血糖状態につながることから発症リスクが増加するとされます。
実際に虚血性心疾患・脳梗塞・2型糖尿病においては、
全く飲まない人と比較して少量飲酒者の方が発症するリスクが低いとされている研究結果もあります。
よく言われる目安としては、ビールで中びん1本(500ml)、日本酒で1合(180ml)です。
ただし高血圧や脳出血、肝硬変、頭頸部がんについては、
少量の飲酒でも発症リスクが高まるといわれ、
総合すると必ずしも「酒は百薬の長」とは限らないということになります。
なぜ、こんなことを書いてみたかというと・・
先日とある食事会で、となりの席の方の会話が耳に入りました。
複数名の中で一人だけ、お酒を召し上がらない方がいたようなのですが
A「お前、酒飲まなくて大丈夫か?」
(私:飲まなくて大丈夫か?の意味がわからん・・・)
B「食事にはお茶の方が合うし、酒はちょっと・・」
A「酒、飲まないと病気になるぞ!」
そーだったのか?!( ´∀` )