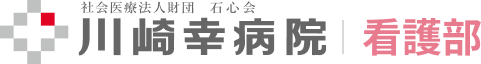続き。
ヒートショック・低体温の危険性と予防対策
大寒波の時期は、ヒートショックによる事故が急増します。
特に高齢の方は、寒さを感じにくくなっているため、知らず知らずのうちに体が冷えてしまい、
入浴時の温度変化がより大きくなってしまいます。
浴室暖房や脱衣所の暖房器具の使用は、命を守る重要な対策ですので、節約を考えずにしっかりと活用していただきたいと思います。
【ヒートショック予防法】
1. 入浴前に脱衣所や浴室を暖房機器で暖めておく
暖房器具を置く、蓋を外して湯を張ると浴室全体を温めることができます。
2. 湯温は41℃以下にし、湯につかる時間は10分程度
熱いお湯に長時間入浴すると、高体温による意識障害が起こる恐れがあります。
ゆっくり、じっくり温まるのが良いようです。
3. 浴槽から急に立ち上がらない
お風呂から出た直後は血圧が急に下がることがあり、立ちくらみや転倒の原因になります。
【低体温症の危険性と対策】
低体温症とは、身体深部の体温(深部体温)が35℃以下に低下した状態を指します。
体温が下がると体内の細胞が不活発になり、消化吸収から思考力に至るまで多くの臓器・身体機能が低下します。
重症化すると意識障害を起こし、最悪の場合は死に至ることもある危険な状態です。
低体温症は雪山や極寒の屋外でのみ起こると思われがちですが、実は室内でも発生します。
日本救急医学会の報告によると、
低体温症で救急を受診した患者の平均年齢は70.4歳で、
屋内発症と屋外発症の比率は約3:1と、屋内での発症が多数を占めています。
低体温症を予防するためには、室温を適切に保つこと(WHO推奨の18℃以上)、
温度計で客観的に確認すること、適度な運動により熱を生み出す力を維持すること、
温かい食事を積極的に摂ることなどが重要です。
【感染症予防と免疫力向上対策】
冬は風邪やインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症が流行しやすい季節です。
気温の低下と湿度の低下により、ウイルスが空気中で長時間生存しやすくなること、
屋内で過ごす時間が長く人同士の接触機会が増加することが、感染症が広がりやすい原因として挙げられます。
ちなみに5類へ移行したとはいえ、コロナ感染症もはびこっています。
こまめな手洗い、アルコール消毒液による手指消毒、マスク着用、咳エチケットの実践が重要です。
【免疫力向上のための生活習慣】
十分な休養
バランスのとれた栄養
質の良い睡眠
適度な運動
適切な湿度管理(50%〜60%)
空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。
乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な湿度を保つことも効果的です。