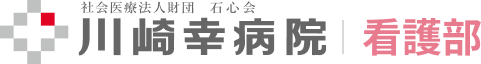最近は中断してばかりのブログです。。。
少々長めの梅雨が明け、あっという間に猛暑日を更新しています。
そういえば、雨の中でセミが頑張って鳴いているのを聞きながら、
もう7月終盤だったなどと考えていたのですが、
8月中旬を過ぎていました。
普段の年ですと、夏休み(帰省)を頂いている時期ですが、
今年は実家から帰省禁止令を出されたため、仕事中心になっています。
そして
今朝の出勤時に、マスク姿の小学生達の登校シーンに出会いました。
もう学校始まるのですか。
こんなに暑い中、教室の空調管理は大丈夫でしょうか。
コロナと熱中症対策は、同時並行するには厳しいかと考えてしまいました。
というより夏休みは何処にいってしまったのでしょう。
人生最短の夏休みという思い出でしょうか。