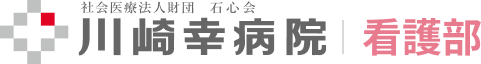3.11 あの日あの時を忘れない
昨日は緊急連絡訓練が来ました。
メールで
・安否確認
・病院までどのくらいの時間で参集可能か
などに応えるものです。
実際の訓練は当院防災チームにより、定期的に開催しています。
#キオクのバトン
あの日、何をしていましたか?
2011年3月11日 東日本大震災 あれから9年・・・
揺れた瞬間、何をしていたんだろう
どうやって家に帰ったんだろう
いつ家族や友人と連絡が取れたんだろう
もう一度、あの日を見つめる伝承プロジェクト
by NHK