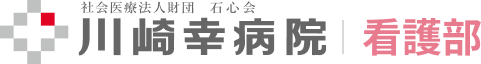ケースレポート発表お疲れ様でした。
1年間、覚える事、実践、多くの学びがあったと思います。
ここでは1年間の自分の看護を振り返るという体験に軸を置いています。
自分の経験・経験知をまとめるという体験です。
形式にこだわる必要はないですが、一定の形に沿って文章にしてみる、これは
自分の頭の中を整理することにつながります。客観的に振り返るという体験ができます。
さらに話す、発表するという体験です。
よく知識の定着は人に教える、人前で話すということが関わると言われます。
また、他者の発表を聞くというのは、
ただ聞くだけではなく、自分に置き換えて考えてみる作業が重要です。
自分はどう感じたか、自分ならどう対処するか?
他者の発表はつい受け身になりがちですが、能動的聞き手になりましょう。
今日まとめたケースの内容を忘れずに、看護を語る経験も積んで欲しいです。
一冊の本を紹介しました。
確か去年も話したのですが(誰も覚えていなかった・・・・( ノД`)シクシク…)
鎌田實 「言葉で治療する」
看護部の理念にコミュニケーションを入れていますが、言葉というのは本当に大切なので
興味のある方は読んでみて下さい。
さて
今年の新人の皆さん、来年の今頃は皆さんの番になります。