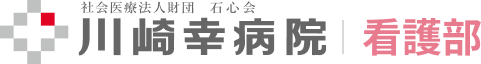昨年に指定研修機関として認可を頂き
開催した「特定行為研修 川崎幸Ver.」の第1期生3名が見事に研修を終了しました。
1年間、業務との両立は本当に大変だつたと思います。
共通科目の学習、テストや演習に加え、
臨床での実習では症例選択しながら、指導医とのディスカッションなど
通常の業務とは次元の違うアセスメント能力を磨いていったのではないでしょうか。
今後は学びから得た、知識を部署へ還元し
さらに後輩たちのロールモデルとなって欲しいと願います。
本当にお疲れ様でした。
そしてこれからもよろしくお願い致します。