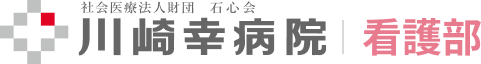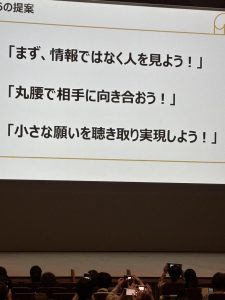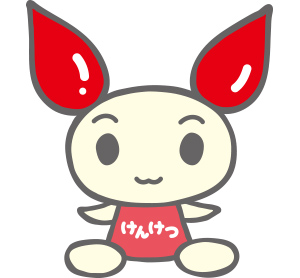休暇が多く福利厚生の充実したところの方が長く勤めやすい環境だと思いますと、、
皆さんが考えておられるようで。
そういえばだいぶ前に、いろいろな施設の看護師夏休み事情を聞いたことを思い出しました。
・正月休み、ゴールデンウィーク、盆休みなどありません。
・連休が取れても2日、よくて3日ですね。人数少ないから休み取ると回らない!
・一応4日間は夏休みとしてあるけど、年間通して使い切ればいいので、有給と同じ感じ。
・公休以外に年末年始の休みとリフレッシュ休暇が2日あるが、夏休みとしてではない。
・夏休みはあるけれど7日以上の休みを取る場合、看護部長の許可が必要。
・夏休みは取った事ないです。コレといって予定も立ててないです。
・リフレッシュ休暇はあるけど普通通りです。まぁ、子どもも大きいので問題ないですが…。
・1年間のどこかで連休を取れればいいかと思っているので夏休みをとるという感覚がない。
皆さんそれぞれですね。
私は新人の頃、オフシーズンに旅行していたので、確かに夏休みは取っていませんでした。
というより今考えると夏休みという制度もなかったような。
看護師の醍醐味は旅行代金のやや下がるオフシーズンに旅行に行けることかと考えたりしていました。
子供ができてからは、実家へ子供を預けて・迎えに行ったことぐらいが夏休み・・・
家族で旅行ということもほとんどせず、仕事に追われ、あっという間に過ぎていた記憶があります。
今年はさらに夏休みという概念がないまま、猛暑・酷暑のせいもあり、
夏がいつから始まり、いつ終わるのかも定かでなく、
気が付いたら9月も過ぎようとしています。
なぜ今頃こんなことを思い出していたかというと、
今朝方から急に気温が下がり、ずいぶん秋めいてきたなーと感じたからでした。
夏休み・・・どうしよう。