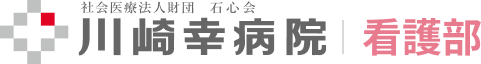戴帽式(たいぼうしき)はナースキャップを戴く式です。
ナースキャップは、看護師の象徴として職業に対するプライドと情熱を誇示する意味を
もっていましたが、現在ではキャップの使用はなくなっています。
看護学生は実習の前に、学習の動機付けとして、戴帽式を行っています。
現在はナーシングセレモニーという行事になっているところが多いようです。
戴帽の儀では、キャンドルを灯して厳かな雰囲気でセレモニーが行われる
のではないでしょうか。
このキャンドルですが、ナイチンゲールの像から灯を自分のローソクに移し、
自分も看護師として患者を見守り続けると言う誓いです。
ナイチンゲールが暗い夜も患者さんのためにろうそくを灯して看護したという言い伝え
から、「看護の光・看護の心の光」とされています。
ランプを手に患者を見回るナイチンゲールは、ランプの婦人と呼ばれていました。
さて先日、とある学生の授業での一コマ。
皆さんが戴帽式で灯したロウソクの灯は何ですか?と尋ねたところ
「LED」との回答がありました。
現代はLEDなのか・・・いや、そこじゃない!
ロウソクの灯の意味をたずねたのでありますが、日本語の難しさを痛感しました。